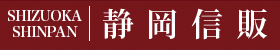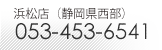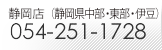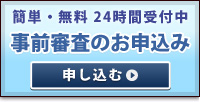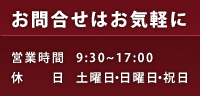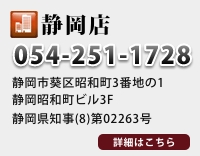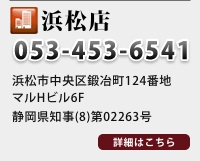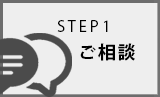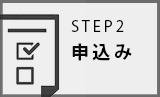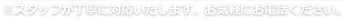千人塚古墳(富士市)
千人塚古墳(せんにんづかこふん)【富士市神谷・市指定史跡】
120基以上からなる須津古墳群の1基。
2002年に発掘調査され金銅製の優品を含んだ武器・馬具などが出土した。
7世紀前半〜中頃の築造と推定されている。
(埼群古墳館HPより 抜粋)
横沢古墳(富士市)
横沢古墳【富士市大渕】
横沢古墳は、大淵横沢の伝法沢西岸に6世紀後半(1400年ほど前)につくられたと考えられる横穴式石室を持つ円墳です。
石室内からは、人骨や馬具、直刀、金銅製の鈴、土器などの副葬品が出土しました。
とくに金銅製の鈴は全国的にも貴重な物で、博物館に展示されています。
広見公園周辺には、6〜7世紀に造られた古墳がたくさんあり、その多くは土の中で深い眠りについています。
(富士市立博物館HPより抜粋)
岩淵の一里塚(富士市)
岩淵の一里塚(いわぶちのいちりづか)【富士市岩淵・県指定史跡】
「一里塚」とは、一里(約4キロ)ごとに街道の両側に土を盛り、土崩れを防ぐため頂上には樹木の「榎」(えのき)が植えられ旅人たちに里程標(道しるべ)を知らせた塚(土盛り)です。
江戸時代に東海道 江戸日本橋を起点にして京都間に104の塚が現存しました。
岩淵の一里塚は 江戸日本橋から37里になります。
(江戸時代 道しるべの「一里塚」 岩淵の一里塚 より抜粋)
伊勢塚古墳(富士市)
伊勢塚古墳【富士市伝法・県指定史跡】
玄竜寺境内にある2段築成の大型円墳で円筒埴輪をともなう。
幅7〜8mの周溝が巡りその形状は馬蹄形(現地案内板ではホタテ貝形)である可能性が指摘されている。
6世紀初頭前後の築造と推定されている。
潤井川流域では最初に築かれた首長墓と考えられている。
(埼群古墳館HPより 抜粋)
庚申塚古墳(富士市)
庚申塚古墳【富士市東柏原新田・県指定史跡】
全国的にも非常に珍しい双方中方墳(中央の木立の下が中方部で左右が双方部)とみられており、すぐ近くの山の神古墳と近い時期(5世紀から6世紀)の築造と推定されている。
ただ未発掘なので墳形は確定ではないと思う。
埴輪は認められず葺石が施されている。
(埼群古墳館HPより 抜粋)
浜松店053-453-6541
静岡店054-251-1728