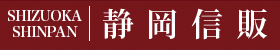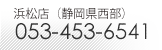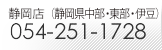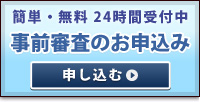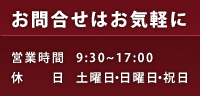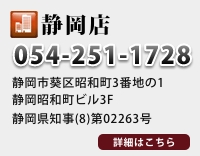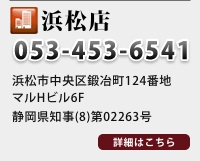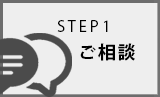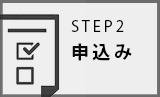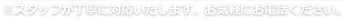玉井寺一里塚(清水町)
玉井寺一里塚【駿東郡清水町】
慶長9年(1604)江戸幕府は、主要な街道沿いに江戸日本橋を起点として1里ごとの道程標識として一里塚を作りました。
五間四方の土地に半球状に十尺の土盛をし、頂上に榎などの木を植えたものが標準形とされています。
町内には2つあり、東海道を挟み伏見玉井寺と宝池寺の前に一対をなしています。
宝池寺側のものは昭和60年に作った冬至と同じ寸法で復元されたものですが、玉井寺側の一里塚は樹木におおわれているもので、作られた当初のものといわれています。
これらは、江戸から29里目にあたり、また、宝池寺境内には立場と呼ばれた茶屋があり道ゆく旅人に湯茶のサービスをしていたといわれています。
この一里塚は長沢に残る東海道松並木とともに昔の東海道を偲ぶことができる史跡です。
(清水町観光協会HPより 抜粋)
智方神社(清水町)
智方神社【駿東郡清水町】
祭神は、主神に大塔宮護良親王、副神が菊理媛命、予母都道守神、藤原千方である。
創建年代は不明であるが、明暦3丁酉年(1657)11月、火災のため旧記録焼失。
貞享元年(1684)に造営したが、その後大破したため、寛延3年(1750)3月に本社を普請したと記録がある。
境内社のひとつである穂見神社の御神木となっているクスノキは、町内最古(推定樹齢700年)で最大のクスノキであり、町指定文化財(天然記念物)となっている。
建武2年(1333)、後醍醐天皇の皇子である護良親王の従者が、皇子の御首を携えて黄瀬川のほとりに逃げ延びてきた折、もう逃げられないとあきらめ、皇子の御首をこの地に埋めた際に墓印として植えたものと伝えられている。
(じゃらんHPより 抜粋)
根方街道(清水町)
根方街道【駿東郡清水町】
根方街道は愛鷹山の南裾を通る道で東海道の古道でした。
(地図の赤線)原と吉原の間にある浮島沼が大きな湖だったために、山裾の道を使っていたのでしょう。
東海道(地図の青線)が整備されてからも東海道の裏道として使われており、現在は(静岡)県道22号線がほぼ同じ道を通っています。
伏見古墳4号墳(清水町)
伏見古墳4号墳【駿東郡清水町・町指定史跡】
本古墳は、静岡ガス伏見供給所南川の台地上にあります。
土師器・須恵器・古銭・人骨が出土。
8世紀末〜9世紀初頭の築造と推定され、古墳の形態をもつ墳墓としては異例の遅さ。
発掘調査後、現状保存された。
(埼群古墳館HPより 抜粋)
千貫樋(清水町)
千貫樋【駿東郡清水町】
三島の楽寿園に湧く小浜池の水を玉川、伏見、八幡、長沢、柿田(後に新宿を加わる)の5ヶ村の灌漑用水として利用するため、伊豆と駿河国境の谷に架けた樋です。
この樋が初めて架けられたのはいつの時代か諸説ありますが、応仁(1467ー69)のころ既に架設されていたようです。
当時樋は木製で長さ39間、幅1間、深さ15寸、高さ1丈5尺ありました。
この樋の維持管理費は、それぞれの村が決められた長さの分負担しあいました。
千貫樋の名前の由来は
- 架樋の技術が素晴らしく、銭千貫に値する。
- この用水が高千貫の田を潤している。
- 架樋費用が銭千貫かかった。
と3説りますが、いずれも樋を賞賛して名付けたものと思われます。
現在の樋はそれまでの木製の樋が関東大震災により崩壊したため、大正3年、鉄筋コンクリート製のものに作り替えたものです。
(清水町観光協会HPより 抜粋)
浜松店053-453-6541
静岡店054-251-1728